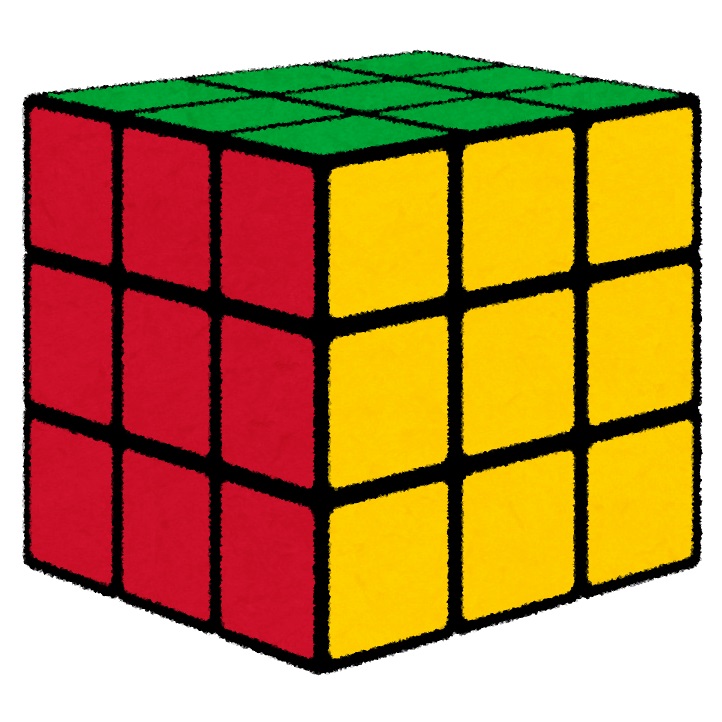北から南まで急に暑くなりましたね・・・
暑ければ暑いほど思考も鈍る、
なにも考えずに扇風機の前で寝ていたい、「カムイさん」です。
本日のテーマは、
「話し合いの落とし穴」です。
人生の中で、避けては通れない
「会議」「ミーティング」「打ち合わせ」・・・
「正解がある、答えが複数あっても最適解がある」
という、客観的な要素に基づいて答えを探すような議題は
業務内でよくありますが、
「主観的で、内面的で、人の価値観によって答えが違う」
という、答えがあるようでないような議題が必要になることがあります。
この主観的で内面的な議論に対して、
感じたことを書き残しておこうと思います。
Next C.T.Lでの事例
最近のNextCTLの議題で挙がった、
「帰社日に全社員が帰社する」というテーマ。
具体的に帰らない人の事例を挙げ、
それに対する対策を練るのは
前者の客観的な視点での話し合いで、
どうして帰らなくてはいけないのか、
どうして帰ってほしいのか、
そもそも帰社とは………?
具体的な対策の前に、
前提条件、芯となる部分の認識合わせをするのは、
後者の主観的な視点での話し合いと捉えました。
主観的な内容を含む話し合いというのはとても難しく、
いくつかの落とし穴が潜んでいます。
- 議長による意見の取捨選択
- 参加者内での前提条件不一致
- 反対意見の出にくさ
などなど……
主観的な話し合いの難点は、
人の「思い・価値観」が要素となること。
議長が「思い・価値観」を脇に置いて進めないと、
どうしても議論の方向性が誘導されてしまうことがあります。
また、
現在どういう状況で、
どういう目的のために、
何を話し合うか?
こういった認識のズレが生じると、
ズレていると気づかないまま議論が進み、
最終的におかしなゴールに辿り着く、
結局スタートに戻っている、ということが起こり得ます。
そして、
具体的な根拠を示すのが難しい分、
一度出た意見に対して反対意見や指摘をしづらく、
議論の勢いに流されてしまいやすいです。
落とし穴にハマった状態で陥るのが、
会議の目的自体があやふやになる
という状況。
「あれ、今日は何の答えを出すための話し合いだっけ???」
と、話が進んでいくうちに、
元々の大目的からズレていってしまったこと、
ありませんでしたか…?
落とし穴を回避するためには
- 話し合いの中に違和感を感じる
- 感じた違和感を言語化する
- 流れを止めて前提に立ち返る
という段階が必要ではないでしょうか。
違和感の言語化は特に難しいですが、
その違和感が致命的なことだったりもします。
(慣れない者同士の議論であれば特に)
定期的に議論を止める時間を置き、
一旦議論や認識のズレがないか確認する。
しつこいくらいに、
「なんのための話し合いだったっけ、
今はそのためのどの部分について話してたっけ?」
という確認をいれていくことも
必要なのではないかなあと感じました。
おまけ:辞書をひいてみた
余談ですが、話し合いを表すそれぞれの言葉を、
辞書で引いてみました。
- 会議 ⇒ 関係者が集まって相談をし、物事を決定すること。
- ミーティング ⇒ 打ち合わせや連絡のための会合。
- 打ち合わせ ⇒ 前もって相談すること。下相談。
会議は「決定」を下す必要があって、
ミーティング・打ち合わせは「集まる事、認識共有すること」が主体目的
……なのかな?
優れた決定なのか、
認識の擦り合わせなのか、
意見の共有なのか、
今自分が出席しているものの、
会合としてのゴール認識が一致していることも、
とても大事ですね!